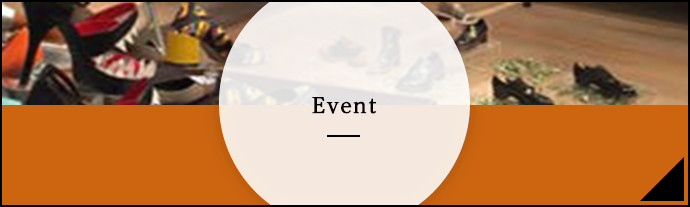シューワード玉手箱
男の靴
男の靴は──最低必要な、基本の靴だけあればよい。ローファーと、スニーカーと、プレーントウの紐じめと、ワークブーツと、この四足があればよい。そして、よく磨き、修理に出し、何年も何年もはいてほしい。
靴は男の顔である。靴の汚れ方でその人の性格やセンスまであらわにする。
靴に妥協は禁物。冷静な選択眼で厳選のコレクションを目指したい。靴にこだわる、というその心情こそ紳士たる所以であり、そうしたこだわりを通して、男にさらなる磨きがかかるのである。
男は、いざサバイバルという時に絶対信用できる一足の靴を持っていたい。
靴は修理して長く履くもの、というように考えているので、私にとっての小道具としての靴は分身のようなものである。
靴は歩くための道具。持ち主がどんなに大切にしていても、全体重でもって地面に擦りつけられ、汚れ、傷つき、磨り減っていく。だからこそ、一緒に歳を重ね、傷やシワやシミを重ねることのできるような靴を探して欲しい。良い靴とはそうして生まれるものです。
靴は身体を装飾する最終のサインです。ボリューム、形、色、すべてのバランス、また全体の着こなしとの統一が取れ、そして履く人にマッチしていなければなりません。
きちんとした身なりの際はヒモで結ぶ靴の方が望ましい。アメリカのビジネスマンのマナーの本には、面接のときなどにスリッポンをはいていると、「この人は靴ヒモを結ぶのを面倒がるタイプだ」と見られ減点される可能性が高い、と書いてある。
おじさんたちが疲れているのは分かるけど、そのかっこう、あまりにヒドクない?──つま先のシワが、どうしてもギョーザを連想させてしまうローファーまがいの靴。その靴に付いている小さな小さなワンポイントの金属片。あれは、いったい何なんだ?
私は靴が好きだから、いろんな靴を買う。しかし、甲高幅広偏平足の私の足に、最初からフィットする靴は少ない。ヨーロッパや英国の、どんな高価な靴でもそうだ。しかし、やはりいい靴ははきたいと思う。というわけで、無理を承知で外国製の靴を自分の足に合わせる工夫をする。若い頃は買ったばかりの靴を鍋で煮たり、靴をはいたまま風呂に入ったりした。
父は身綺麗で几帳面な人であったが、靴の脱ぎ方だけは別人のように荒っぽかった。──父は生まれ育ちの不幸な人で──物心ついた時からいつも親戚や知人の家の間借りであった。履物は揃えて、なるべく隅に脱ぐように母親に言われ言われして大きくなったので──十年、いや二十年の恨みつらみが、靴の脱ぎ方にあらわれていたのだ。
靴とのつきあいは女房よりずっと古いのだが、もう泣かされてばっかりだ。──女房とうまくやっていくのも疲れるものだが、靴と円満にやっていくほうがもっと疲れる。
他が完璧で靴だけ情けない、というのは、彼女のために最高級のデートコースを設定し、いよいよ最後の詰めというところで立たなかった――そんなインポテンツ的な状況を思い浮かべてしまう。
足を圧迫するブーツは男性的な権力の象徴である。
デザートブーツは若者向きと思われているが、いい大人が履いてこそよりふさわしい印象を与えると私は思っている。
散歩に一番適した靴は何かと言えば、僕はワラビ―ブーツにとどめをさすと思う。
エドワード・グリーンの靴は、長い間履き続けていると、その良さがジワッと分かってくる。その贅沢な履き心地の良さの秘訣は靴底にあるようだ――「当社には八代にわたり、靴底を専門に作り続けている職人がいる。それは選び抜かれた雄牛の皮を自然の樹皮と樫の実を使って鞣して作られる」
マックスウェルの靴は、消耗品とは考えにくい性質を持っている。それは身につける芸術品であり、最大級の満足であり、贅沢にして完璧な生活の道具なのだ。──持ち主と同じだけ生き残る、そんな物作りが常識的に行われていることに驚くのみだ。
プラダのメンズは90年代のモード界に濃縮した業績を残した。ともすれば、服の“バイプレイヤー”的存在だった靴を、ファッションの“主役”の座に押し上げたともいえる。
僕は外では紺のダブルのスーツしか着ないんです。それで、紺に一番合う靴といったら白ですよね。だから僕はこの靴、ニチマンの白のズック靴しか履かないんです。もう何年もそうだから、たぶん200足は履いたかな。
靴といえば私たち日本人と靴の本場のヨーロッパやアメリカの人たちとは根本的に考えが違う。──要するに私たちは外出するからそのときは靴を履くが家に戻れば素足でくつろぐことができる。日本人の靴とはそういうものなのだ。だから私は日本人の足に合わせて作られているリーガルシューズを愛用している。