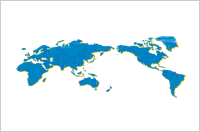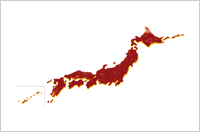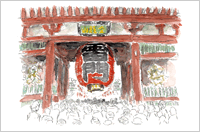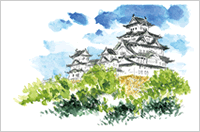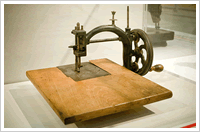Column
1000年以上の歴史がある日本の革文化
日本の革の歴史は、飛鳥時代以前に大陸から渡来した人々によって、革の加工技術の多くが伝えられたとされている。ここでは、歴史とその地域の特性を紹介していく。
皮革の加工文化は、民族によって多様である。気候、風土、生活様式、文化などによって加工方法は変わるからだ。ヨーロッパなどの大陸の場合、近隣地域との交流によって、さらなる技術がもたらされる場合も多かったという。
日本の場合、大陸から渡来した「熟皮高麗(おしかわこま)」「狛部(こまべ)」といった呼称の工人たちが革の加工技術を伝えた。つまり、日本の革の歴史は、1000年以上も前にさかのぼることができるのだ。播州姫路地方で当時より革のなめしが盛んに行われ、なめしの工程は、瀬戸内海産の塩による原皮処理→浅瀬で洗い流し→石河原での川漬→脱毛→塩入れ→加湿→菜種の油付け→揉み→さらし→革洗いの反復作業で行われていた。海が近い姫路は、まさに革の加工にピッタリの土地だったのだ。
そのほかの地域でも、同様の技術によって革の加工が行われていた。日本が諸外国に門戸を開く江戸時代までこの技術で革の加工がされ、革は鞍や文庫などに珍重された。現代の主流となっているタンニンなめしやクロムなめしは、明治時代になって伝えられ、現在にいたる。
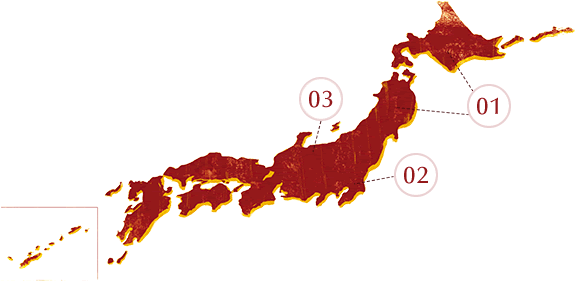
独自の文化が栄えた北海道地域
北海道は独自の気候と、冬場の厳しい自然で知られる。その地ではどのような皮革が伝えられてきたかのかというと、古くから発展してきたアイヌ文化では、獣皮だけでなく鮭の皮もなめして靴などの日常用品に使われていた。馬の育成や牧場などが飛鳥時代より多数ある東北地方では、履物製造に歴史があり、現在でも山形県や福島県では地場産業としてその技術は伝えられている。
家内制手工業的な技術発展
東京では袋物の製造が盛んに行われてきた。浅草周辺では袋物に限らず、靴、ベルトといった革製品の工場が軒を連ねている。また、その原料となる革を供給すべく関東近郊には、なめし工場も多数ある。東京に限っていえば豚革。隅田川、荒川など大きな川があり、革のなめしに適した土地柄で、家内制手工業的な規模の工房も多い。その他、特徴的なのは爬虫類などのエキゾチックレザーの加工工場も多い。
鹿革加工の甲州印伝が今も伝わる
特筆すべきは、甲州印伝だろう。鹿革に模様を付けたもので、ふすべ技法と漆で加工したものがあるのが特徴。武具や小物などに使われてきた。甲州印伝は、江戸時代中期に幕府に献上されたインド装飾革を、国産化したものが起源。全国各地で製造されていたが、今でもその技法は甲州に伝えられている。時代とともに製品は形を変えて、バッグなどに使われるようになり、その人気は根強い。
【 鹿革 】
日本でかつて多用されたのは鹿革。馬の脳髄から取り出した「脳漿(のうしょう)」で革をなめしていた。この技術は昭和30年代まで各地に伝承されていたが、今では終焉してしまっている。また、なめし終わった鹿革の白革をいぶして染色を行うのが、ふすべ(熏べ)革だ。これが現在では数少なくなった、印伝の作り方のひとつ。
関西、山陽・山陰、四国、九州の革文化